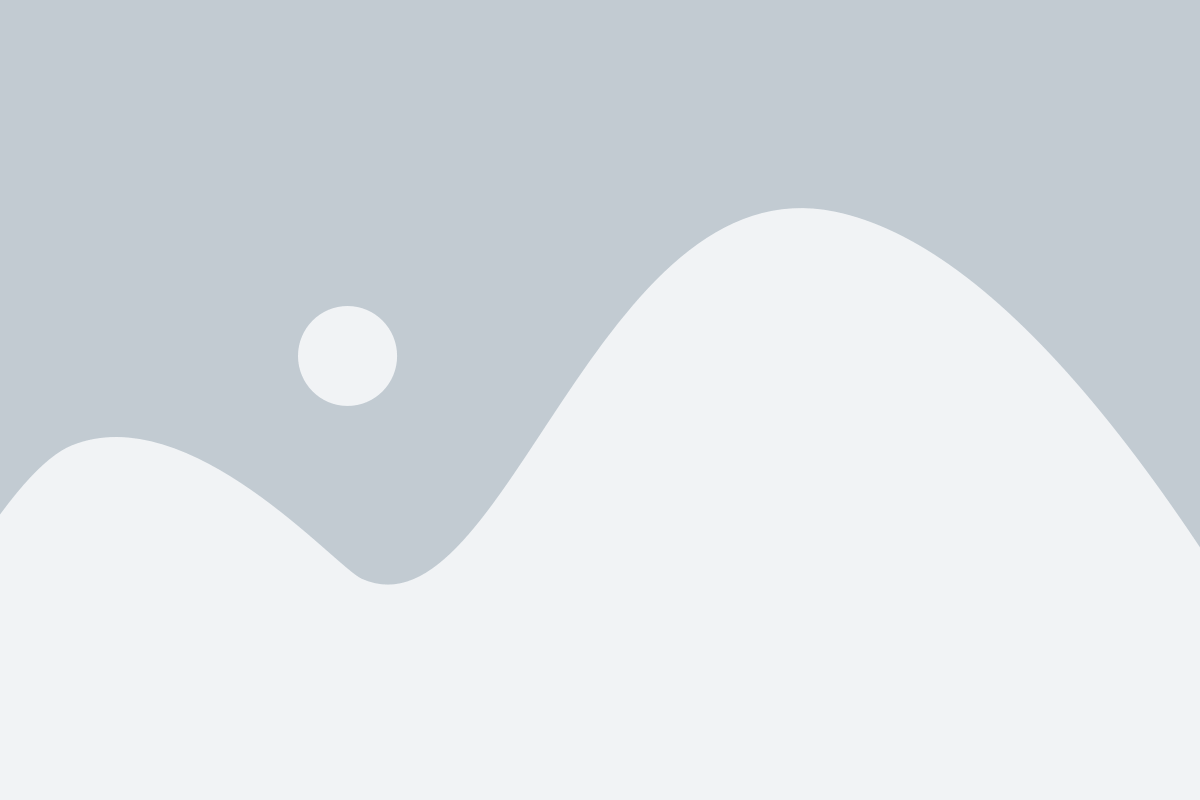今月は、外来後発医薬品使用体制加算の算定について解説致します。
●外来後発医薬品使用体制加算の留意点
外来後発医薬品使用体制加算の算定にあたっては、施設基準の届出(直近3ヵ月の実績)を行った上で、後発医薬品の使用割合に応じて、1処方につき処方料に加算します。
・外来後発医薬品使用体制加算1(1処方につき) 8点(90%以上)
・外来後発医薬品使用体制加算2(1処方につき) 7点(85%以上)
・外来後発医薬品使用体制加算3(1処方につき) 5点(75%以上)
●施設基準の解説
(1)診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている。
(解説)薬剤部門に薬剤師の配置は必須ではありません。医師が配置(兼務可)され、後発医薬品の品質、安全性、安定供給等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていることとされています。また、後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・氏名等、検討する内容、開催回数等を明確にしておく必要があります。
(2)保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価に規定する規格単位ごとに数えた数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。
(解説)計算式は下記となります。
(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
(解説)計算式は下記となります。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
① 経腸成分栄養剤
エレンタール配合内用剤、エレンタールP 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
② 特殊ミルク製剤
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
③ 生薬(薬効分類番号510)
④ 漢方製剤(薬効分類番号520)
⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
(5) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
(6) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
(7) (6)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8) (5)及び(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
●おわりに
外来後発医薬品使用体制加算の算定に向けて、現状の後発品の使用割合をご確認頂くことで、クリアできているかもしれませんし、処方頻度の高い薬剤を後発品に変更することで算定できる場合もあります。また、既に算定している医療機関では、2024年6月の診療報酬改定において、基準(6)(7)(8)は追加されているため注意が必要です。

能見 将志(のうみ まさし)
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。