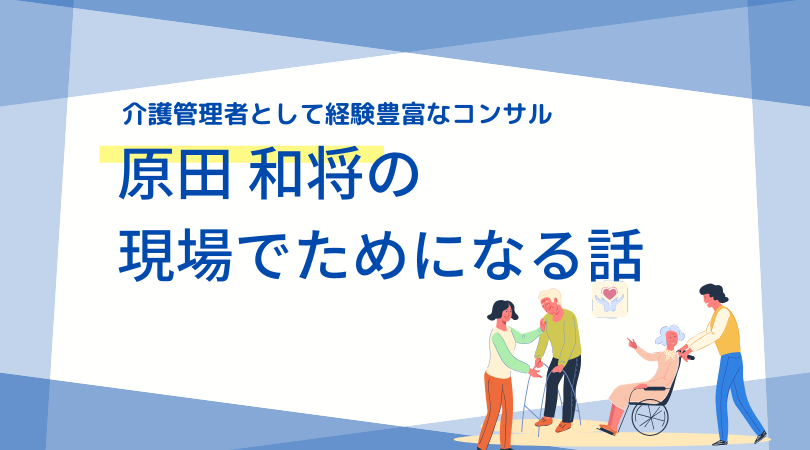NHKの調査によると、訪問介護事業所が1つも存在しない自治体は全国で109、1つしかない自治体も268にのぼります。全国の5分の1以上で、訪問介護の提供体制が極めて脆弱である実態が明らかになりました。2023年度には、全国で529件の訪問介護事業所が倒産・廃業しており、過去最多を記録しています。背景には、人手不足や物価の高騰、介護報酬の引き下げといった複合的な要因があります。中でも大きな課題となっているのが、担い手であるホームヘルパーの確保です。訪問介護員(ホームヘルパー)の平均年齢は54.4歳と介護職種の中で最も高く、60歳以上が37.6%を占めるなど、深刻な高齢化が進行しています。今後、ベテラン人材のリタイアが加速することにより、地域によっては支援体制の維持がさらに難しくなることも懸念されます。
熊本県産山村では、唯一の事業所が撤退した後、隣接する阿蘇市から週2回だけヘルパーが派遣されるという“綱渡り”の支援が続いています。長距離移動による時間的な制約や燃料費の負担は、事業所の経営にも影響を及ぼしており、サービス継続に対する不安は拭えません。こうした状況の中、国は「施設から在宅へ」の方針を掲げ、住み慣れた自宅での看取り体制の構築を進めています。しかし、この方針の実現には、訪問介護という地域支援の基盤が安定していることが不可欠です。
一部の自治体では、高校での職業訓練を通じて介護の魅力を若者に発信する取り組みが行われており、一定の成果も見られます。今後は、こうした新しい力を呼び込むための取り組みを継続するとともに、既存の支援体制を守るための対策も同時に講じていく必要があります。地域包括ケアシステムの構築に向けては、地道で実効性のある取り組みが求められています。
原田 和将
一般社団法人 アジア地域社会研究所 所属
介護現場での管理者としての経験を活かした職員研修、コーチングを中心に活動。コーチングはITベンチャーなど多岐にわたる業態で展開。国立大学での「AIを活用した介護職員の行動分析」の実験管理も行っており、様々な情報を元にした多角的な支援を行う。