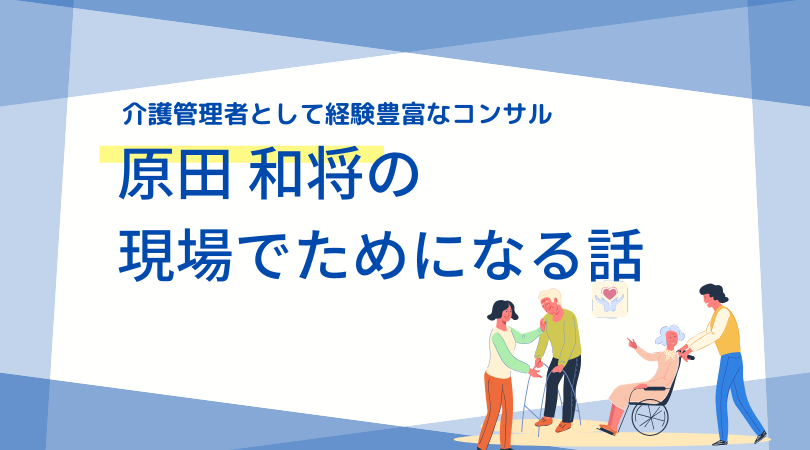近年、ハローワークを通じて就職を希望する高齢者や障害者の数が大きく増加しています。厚生労働省によれば、2023年度の高齢者の求職者数は約27万人、障害者は約23万人と、いずれも10年前の2倍に達しました。これは、定年後も働き続けたい高齢者や、障害を持ちながらも社会参画を望む人々が確実に増えている現実を映し出しています。これを受け、厚労省は専門の就労支援員の増員、職業訓練や企業とのマッチング強化、さらに福祉専門職との連携など、ハローワークの機能を一層拡充する支援体制の強化に乗り出しました。です。従来の「紹介するだけ」の機関から、「伴走し、育てる」体制へと進化を遂げつつあります。
こうした流れは、私たち医療・福祉の現場にも直接的な示唆を与えてくれます。重要なのは、日常業務の中から、高齢者や障害者の方に担ってもらえるタスクを丁寧に抽出していくことです。日常の中で行っている一つひとつの業務を因数分解し、単位ごとで見直すことで、新たな担い手が見えてきます。そしてこの「因数分解の習慣化」は、単に新たなタスクの担い手を創出するだけでなく、業務の可視化・整理を通じて全体の生産性向上にも寄与する可能性を秘めています。すべてを職員が担うのではなく、適材適所の再設計によって、業務全体の効率化と組織の持続力を高める視点が、これからの現場には求められています。これは介護助手やスポットアルバイトの活用にも繋がる部分です。
今、求職者側の「働きたい」という声に、受け入れ側がどう応えるかが問われています。制度が動き出した今だからこそ、組織としても柔軟に変化するチャンスと捉えるべきです。人を活かすとは、業務を見直すことであり、日々のタスクを丁寧に見つめ直すことが、未来の組織の強さを形作っていくはずです。
原田 和将
一般社団法人 アジア地域社会研究所 所属
介護現場での管理者としての経験を活かした職員研修、コーチングを中心に活動。コーチングはITベンチャーなど多岐にわたる業態で展開。国立大学での「AIを活用した介護職員の行動分析」の実験管理も行っており、様々な情報を元にした多角的な支援を行う。