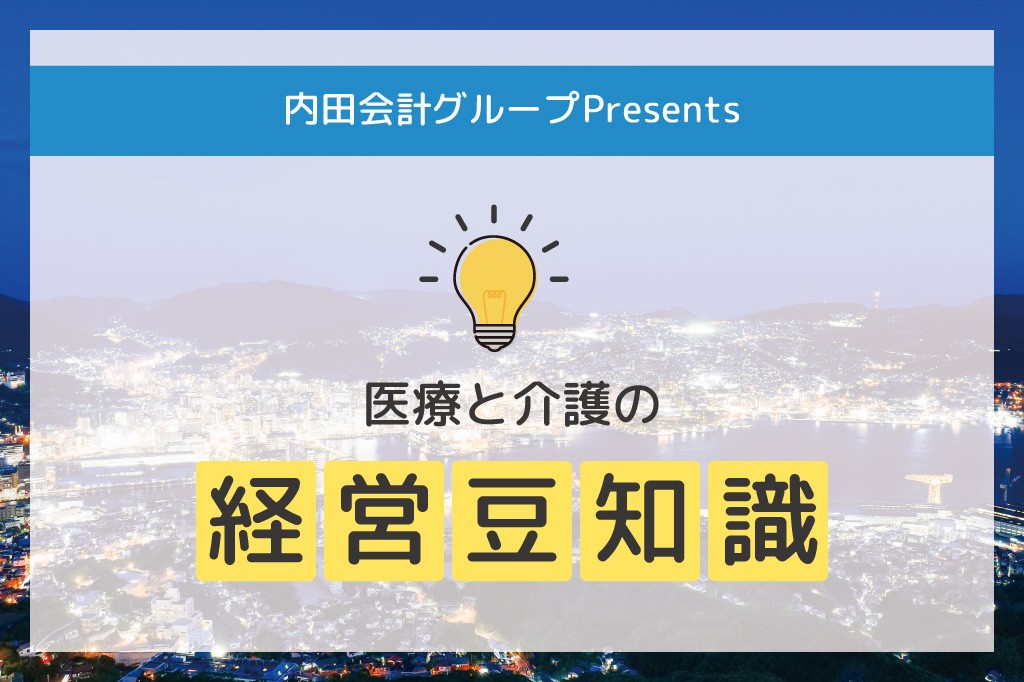社会福祉法人の理事会の決議は、基本原則(社会福祉法 第45条の14)により以下の要件を満たすことで成立します。
定足数:議決に加わることができる理事の過半数(または定款で定めた割合以上)が出席していること。
賛成数:出席した理事の過半数(または定款で定めた割合以上)の賛成があること。
賛否が同数の場合は、「過半数の賛成」には達していないため、決議は否決されたものと扱われます。つまり、理事会での決議は成立しません。未成立の決議については再度理事会を開催し再投票を行うことが可能ですが、時間も手間も掛かります。
社会福祉法人の理事長には、賛否同数時に裁定する権限は法令上明記されていませんが、定款に理事長の裁定権を認める規定がある場合は、その規定に従うこととなります。
その為、定款に明記することが重要です。記載がない場合は理事長の裁定権は認められません。
定款に「賛否同数の場合の扱い」や「理事長の裁定権」についての規定があるかどうかを確認し、無ければ事前に定款変更をしておくことでスムーズに決議を進めることが可能になります。
しかしながら、理事長が最終的な判断を下す権限を持つことになりますので、他の理事とのバランスや透明性の確保は重要であると思われます。
●理事長に裁定権を与える際の注意点
- 法令上の制限はないが、定款で明記が必要
• 社会福祉法では、理事長に賛否同数時の裁定権を与えることを禁止していません。
• ただし、定款に明記されていない場合、裁定権は認められません。 - 理事長の権限が強くなりすぎないよう配慮が必要
• 裁定権を持つことで、理事長の意思が法人運営に強く影響する可能性があります。
• 他の理事とのバランスや、ガバナンスの観点から慎重な運用が求められます。 - 利害関係がある場合は裁定権を行使できない
• 理事長が議題に関して特別な利害関係を有する場合は、裁定権を行使できないようにする規定を設けることが望ましいです。
最後に、この条項は任意的記載事項となりますので、記載するかどうかは法人の運営方針に応じてご判断いただければと存じます。
●参考
厚生労働省:社会福祉法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82001000&dataType=0&pageNo=1