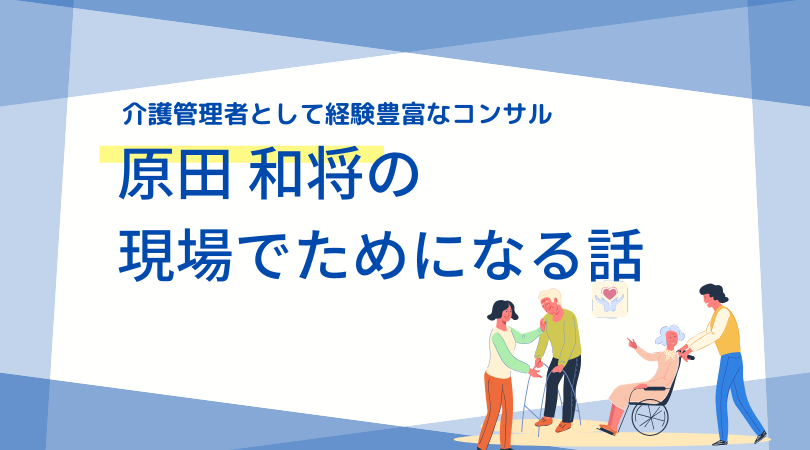近年、高齢者の都市部への移住が加速しています。買い物や通院の利便性、医療・介護資源の豊富さ、子どもの近居ニーズなどが背景にあり、75歳以上の転入者は10年で約3割増えました。一方で、多くの地方では事業所不足や生活上の負担から、高齢者が在宅生活を維持しにくい状況も深刻化しています。
特に問題視されているのが、介護サービスの「地域格差」です。介護保険制度は全国統一であるにもかかわらず、市区町村レベルでサービス供給量には極端な差が存在します。訪問介護事業所がゼロの自治体は全国に多数あり、デイサービスなどの通所系が存在しない市区町村も少なくありません。その結果、同じ介護保険料を払っていても、住む地域によって受けられるサービスが全く異なるという不公平が生まれています。都市部では、施設の空きがなく「介護難民」が増加し、地方では人材不足により訪問介護そのものを提供できない地域もあります。供給バランスの崩れは全国共通の課題となっています。
さらに、2027年の制度改正は地域格差を一段と拡大する可能性があります。要介護1・2の訪問介護や通所介護が介護保険給付から外れ、市区町村の財政力に依存する運営に移行した場合、サービスの質と量はこれまで以上に地域差が出ることが確実です。人口減少が進む地域では財源も人材も不足し、軽度者の支援が十分に確保できないリスクがあります。
こうした構造問題の中で、介護事業所に求められるのは「地域特性に応じた戦略対応」です。ICT化による業務効率化、多機能型スタッフの育成、スポット人材の活用、医療・介護・行政との広域連携など、限られた資源を最大化する取り組みが不可欠になります。高齢者の都市移住が進み、地域間のサービス格差は避けられない流れだからこそ、事業所自らが“選ばれる存在”になるための準備が急務です。
原田 和将
一般社団法人 アジア地域社会研究所 所属
介護現場での管理者としての経験を活かした職員研修、コーチングを中心に活動。コーチングはITベンチャーなど多岐にわたる業態で展開。国立大学での「AIを活用した介護職員の行動分析」の実験管理も行っており、様々な情報を元にした多角的な支援を行う。