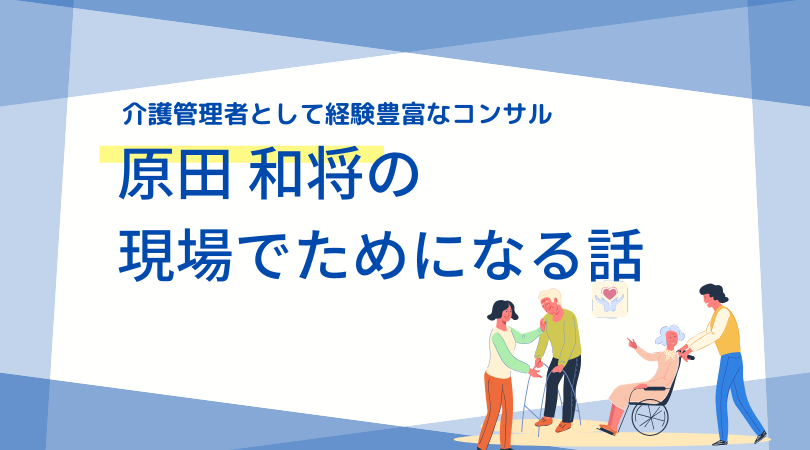地域包括ケアシステムを機能させるためには、「住まい」のあり方を見直すことが避けて通れません。2024年の国民生活基礎調査では、65歳以上の高齢者において「単独世帯」が初めて最多となり、従来の“家族介護”に依存した構造は大きく崩れつつあります。特に80歳以上の女性では、3人に1人以上が一人暮らしという現実があり、これは介護が必要になっても頼れる家族が身近にいない人が急増していることを意味します。 こうした中、政府が打ち出した「高齢者向けシェアハウス整備」は、効率的で持続可能な地域包括ケアの仕組みを支える有力な一手となり得ます。2028年度までに全国100カ所の整備を目指し、既存施設を活用して低料金で入居できる住まいを整備します。社会福祉法人やNPOが運営主体となり、介護サービスを併設しながら住民同士の緩やかな助け合いを促進していきます。
このモデルは、単なる「住居提供」にとどまらず、孤独や介護難民といった課題にも直接アプローチします。警察庁のデータでは、2024年だけでも約6万8000人の高齢者が孤独死したと推定され、地域とのつながりを失うことが深刻なリスクとなっています。シェアハウスという共生型住居は、自然な会話や家事分担の中で、役割や生きがいを再発見できる環境を提供します。もちろん、住み慣れた家を離れる心理的抵抗や、制度の未整備といった課題は依然として存在しますが、「ここでなら暮らしたい」と思える空間とスタッフ、同居人との人間関係をどう築くかが、鍵となっていくはずです。
地域包括ケアを「理想」から「実装」へと進めるには、医療・介護・生活支援を包摂する“暮らしの基盤”が必要です。高齢者シェアハウスは、まさにその起点となる可能性を秘めています。
原田 和将
一般社団法人 アジア地域社会研究所 所属
介護現場での管理者としての経験を活かした職員研修、コーチングを中心に活動。コーチングはITベンチャーなど多岐にわたる業態で展開。国立大学での「AIを活用した介護職員の行動分析」の実験管理も行っており、様々な情報を元にした多角的な支援を行う。