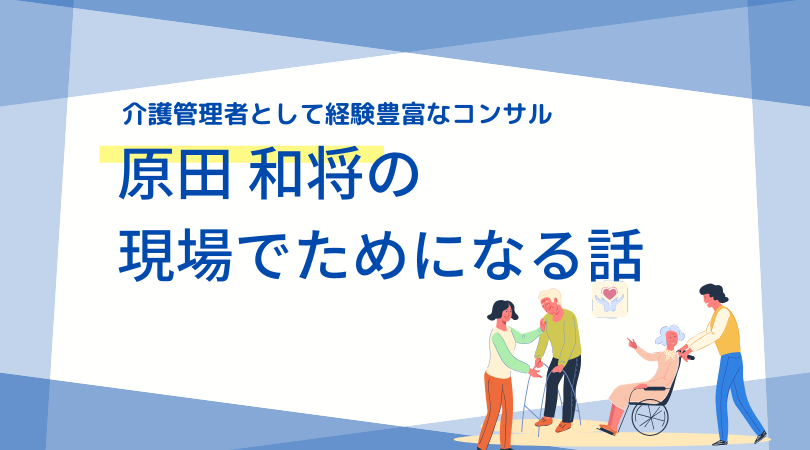R7年10月9日、社会保障審議会介護保険部会から「地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)」について資料が公開されました。2040年を見据えた地域包括ケアシステムの深化を目的に、高齢者支援・地域共生・災害対応を一体的に再構築する方向性が示されています。
特に重要なのは、人口減少・高齢化の進行を前提に、行政や福祉分野の枠を超えて「地域ぐるみの支援体制」を整えることです。身寄りのない高齢者が増加する中で、ケアマネジャーや地域包括支援センターが個人対応だけでなく、地域課題として生活支援・財産管理・身元保証・死後事務まで包括的に取り組む必要があると指摘されました。
これに対し、地域ケア会議を中核に、司法書士・金融機関・民間事業者・住民団体など多様な主体が連携し、支援資源を可視化・共有していくことが推奨されています。また、地域包括支援センターの業務量過多に対応するため、介護予防支援やケアマネジメントの一部委託、ICT・AIの活用による負担軽減も進められています。
一方で、災害時対応においては、約8割の地域包括支援センターがBCP(業務継続計画)を策定しているものの、実効性や連携面に課題があり、平時からの顔の見える関係づくりと多機関連携が求められます。
さらに、中山間・人口減少地域では、高齢・障害・子ども・生活困窮支援を一本化し、福祉以外の分野(交通・住まい・労働など)も含めた地域協働の仕組みを制度化する方針が示されています。これにより、重層的支援体制整備事業の拡充や、都道府県による支援・評価体制の明確化が進む見込みです。
総じて、国は「個別支援から地域全体支援へ」の転換を重視し、住民・行政・民間が一体で支え合う地域共生社会の形成を進めようとしています。
原田 和将
一般社団法人 アジア地域社会研究所 所属
介護現場での管理者としての経験を活かした職員研修、コーチングを中心に活動。コーチングはITベンチャーなど多岐にわたる業態で展開。国立大学での「AIを活用した介護職員の行動分析」の実験管理も行っており、様々な情報を元にした多角的な支援を行う。