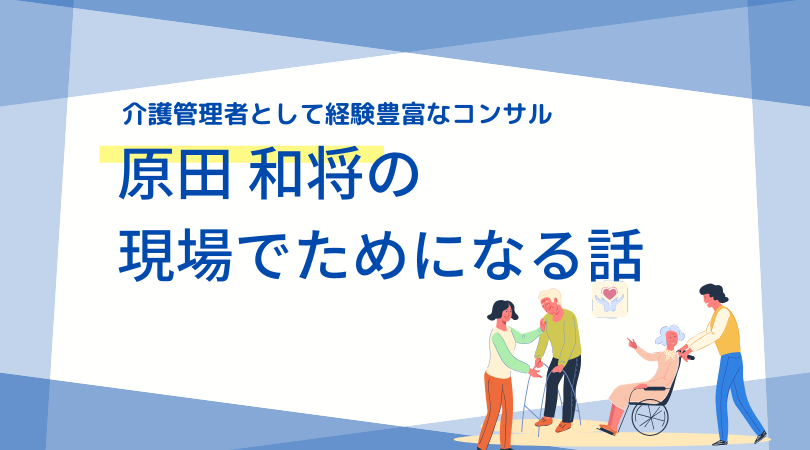2025年上半期、訪問介護事業者の倒産件数が前年同期比12.5%増の45件となり、2年連続で過去最多を更新しました。特筆すべきは、この倒産がもはや零細事業者にとどまらず、従業員10名以上の中小規模にも波及している点です。背景には介護報酬のマイナス改定、ヘルパー不足、ガソリン代や人件費の高騰といった複合的な要因があり、経営の持続可能性は限界に達しつつあります。訪問介護は、在宅での生活を支える要として、高度な信頼関係と個別対応が求められる領域です。地域の小規模事業者が“最後の砦”として支えてきたものの、倒産・廃業が続けば、生活そのものが立ち行かなくなる高齢者が増える恐れも現実味を帯びてきました。こうした現状を前に、単なる経営支援では限界があることは明白です。
その打開策の一つとして注目されているのが、「訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービス」の創設です。介護人材政策研究会は7月、厚労省老健局に対して、同サービスを新類型として制度化するよう要望しました。
この複合型サービスは2023年末に社会保障審議会で議論され、2024年の報酬改定では制度化が見送られたものの、2025年以降の再検討が進んでいます。背景には、訪問介護利用者数が2040年までに150万人を超えるとされる急増予測、そして有効求人倍率15倍超という深刻な人材難があり、「限られた資源をどう効率的に活用するか」が喫緊の課題となっています。すでに、訪問介護と通所介護の両方を運営している法人は全体の半数以上となっています。制度上は分かれていても、運営実態としての土台は整っていますが、現行制度では情報共有などが煩雑で、利用者ニーズに柔軟に対応できないという非効率が顕著です。
複合型サービスには、いくつものメリットがあります。例えば通所で把握した生活状況が訪問支援に活かされ、急なサービス変更にも同一法人内で対応可能となるため、きめ細かく一貫性のあるケアが実現します。また、関わりのあるスタッフが訪問する安心感は、利用者と家族の心理的負担も軽減します。制度設計の複雑さ、人材確保の目処、既存サービスとの調整など、クリアすべき課題は残されていますが、制度上の壁を超えて“多機能型の在宅ケア”を進めていくことは、限界に近づいた訪問介護体制を立て直す鍵となり得ます。
現在制度は大きな分岐点にあります。倒産の増加を「一過性の数字」として片付けるのではなく、地域包括ケアの再設計への警鐘として捉え、柔軟な発想と対応を行っていくことが求められます。
原田 和将
一般社団法人 アジア地域社会研究所 所属
介護現場での管理者としての経験を活かした職員研修、コーチングを中心に活動。コーチングはITベンチャーなど多岐にわたる業態で展開。国立大学での「AIを活用した介護職員の行動分析」の実験管理も行っており、様々な情報を元にした多角的な支援を行う。